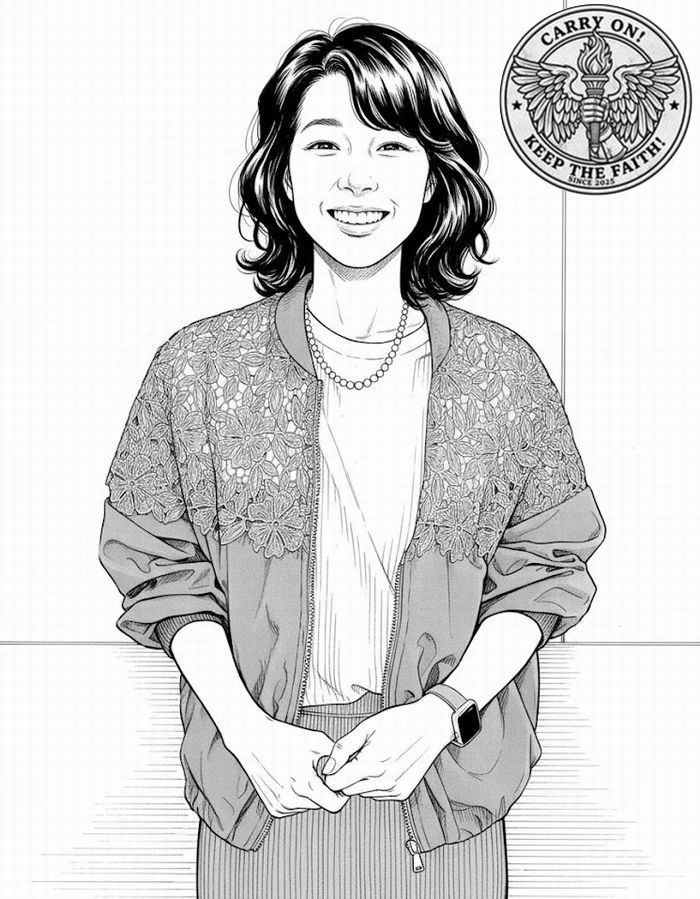【インタビュー・サマリー】 ※誤字・脱字はご容赦を
● 番組オープニングとゲスト紹介
文化放送の『武田砂鉄 ラジオマガジン』のインタビューコーナーに、DJ・ナレーターの秀島史香氏がゲストとして登場した。
秀島氏は大学在学中にラジオDJデビューし、J-WAVEの『GROOVE LINE』などFMラジオを中心に多くの番組を担当してきた経歴を持つ。
ナレーターとして映画、テレビ、CMでも活躍し、通訳や字幕翻訳、コラムや音楽レビューの執筆など幅広い分野で活動している。
武田氏と秀島氏はすれ違いはあったものの、じっくり話すのは初めてで、今回の対談となった。
秀島氏は武田氏の番組を"創刊されたばかりの雑誌"に例え、読みたかったものが詰まっているような印象を持ったと語った。
● ラジオパーソナリティの発声と声のトーン調整
武田氏は声の訓練を受けたことがなく、朝の番組では夜より三割増しのトーンで話すため喉が痛くなると悩みを打ち明けた。
秀島氏は新しい時間帯に慣れることが重要で、発声の調整は「慣れ」が最も大切だと身も蓋もない結論を提示した。
新しい筋肉を使うように、朝の時間帯では自然と声のトーンが上がり、窓から差し込む朝日に合わせて体が反応するものだと説明した。
横浜駅での迷いを例に、慣れない環境では疲れやすいが、慣れてくると自然に対応できるようになると語った。
秀島氏自身も様々な時間帯の番組を担当してきた経験から、体が自然に慣れていくものだと強調した。
● 秀島氏のキャリアの始まりと帯番組の苦労
秀島氏は大阪のFM802で深夜2時から3時の番組でラジオキャリアをスタートし、大学時代に新人公募オーディションに合格した。
4人の新人DJが別曜日でスタートし、1年目で淘汰されるシステムの中で経験を積んだ。
その後J-WAVEでレギュラーを獲得し、大学卒業後すぐに週5のレギュラー番組を持つことになった。
帯番組を始めた当初はアドレナリンで乗り切れたが、2日目、3日目と続くと「もたんわ」という状態に陥った。
最初は大好きなラジオへの情熱だけでやっていたが、次第に話すことがなくなり、深刻なスランプに陥った経験を語った。
● 話すネタの見つけ方と日常からの着眼点
秀島氏は定型文やおしゃれな語りだけでは帯番組は続かないと気づき、日常の小さなことを言葉にする習慣を始めた。
著書『なぜか聴きたくなる人の話し方』の中で、話すことがなくなったら目に見えるものを語ればいいと提案している。
 スタッフが飲んでいる北海道とうきび茶や、相手のバンドTシャツなど、身近な情報をきっかけに話を広げる技術を身につけた。
気の利いたことを言わなければというプレッシャーをかけると固まってしまうため、まず口にする勇気を持つことが重要だと語った。
自分の半径1メートルのことを話すことが、ラジオ、特に帯番組においてリアルな生活感を生み出すと強調した。
● FM的語りとAM的語りの文化的違い
FM的な語りとAM的な語りには文化的な違いがあり、FMでは放送作家が例文を用意することが多いと秀島氏が説明した。
放送作家が2、3、4行の式の例文を跳び箱のジャンプ台のように用意し、それをなぞって読むとFM的な語りになる傾向がある。
「いよいよ秋めいてまいりましたね」「落ち葉も落ちてきているのかしら」といった定型的な表現が典型例として挙げられた。
最近では例文なしで、見たもの、気になったものだけで自由に話す形式も増えてきていると語った。
AM的な生活との距離感を大切にし、帯番組では一緒に暮らしていく感覚でリアルな話をすることが重要だと強調した。
● インタビュー術と相手の話を聞く姿勢
秀島氏はインタビューの大前提として「失礼のないように」という基本姿勢を挙げ、最低限のバックグラウンドをおさらいすることが重要だと語った。
新聞記者のインタビューを例に、質問リストを順番通りに消化するだけで相手の答えを聞いていない「インタビュー下手」な人が多いと指摘した。
会話はあちこち飛ぶものなのに、無理やり第一章、二章と順番に進めようとすると相手は「聞いてくれていたのかな」と寂しい気持ちになる。
うまくいかない日もあるが、その場合は相手の文化やモードに自分が合わせることで対応すると語った。
強引に引っ張るより、ひたすら温めて相手のペースに合わせる「北風と太陽」のアプローチを基本としている。
● 話し方の語尾と間の取り方の重要性
秀島氏は語尾にその人の個性が出ると考えており、武田氏の「何ですかねー」という質問の振り方は相手を追い込まず余白を残すトーンだと分析した。
安住紳一郎氏の「さて」の間が絶妙すぎると例に挙げ、沈黙の後の場面転換が見事だと評価した。
ラジオでは「何秒空いたら放送事故」という都市伝説があるが、実際にはそんなことはないと語った。
言葉を探す間は、聞いている人にとっても情報を整理するための「踊り場」になり、箸休めの役割を果たすと説明した。
ずっと集中して聞かせるギチギチの放送は疲れてしまうため、抜き所や余白を作ることが大切だと強調した。
● 番組クロージングと自然な終わり方
インタビューの終わりに無理にうまく締めようとする必要はなく、「時間ですね」という自然な流れで終わればいいと秀島氏が語った。
お弁当のおかずに例えて、プチトマトを転がしておくような余白が全体を最後まで支えてくれると説明した。
武田氏が著書の内容を引用し、終わり方を考えすぎる必要はないという秀島氏の考え方を確認した。
「またお願いします」という挨拶で終わる自然な形が最も良いという結論に至った。
スタッフが飲んでいる北海道とうきび茶や、相手のバンドTシャツなど、身近な情報をきっかけに話を広げる技術を身につけた。
気の利いたことを言わなければというプレッシャーをかけると固まってしまうため、まず口にする勇気を持つことが重要だと語った。
自分の半径1メートルのことを話すことが、ラジオ、特に帯番組においてリアルな生活感を生み出すと強調した。
● FM的語りとAM的語りの文化的違い
FM的な語りとAM的な語りには文化的な違いがあり、FMでは放送作家が例文を用意することが多いと秀島氏が説明した。
放送作家が2、3、4行の式の例文を跳び箱のジャンプ台のように用意し、それをなぞって読むとFM的な語りになる傾向がある。
「いよいよ秋めいてまいりましたね」「落ち葉も落ちてきているのかしら」といった定型的な表現が典型例として挙げられた。
最近では例文なしで、見たもの、気になったものだけで自由に話す形式も増えてきていると語った。
AM的な生活との距離感を大切にし、帯番組では一緒に暮らしていく感覚でリアルな話をすることが重要だと強調した。
● インタビュー術と相手の話を聞く姿勢
秀島氏はインタビューの大前提として「失礼のないように」という基本姿勢を挙げ、最低限のバックグラウンドをおさらいすることが重要だと語った。
新聞記者のインタビューを例に、質問リストを順番通りに消化するだけで相手の答えを聞いていない「インタビュー下手」な人が多いと指摘した。
会話はあちこち飛ぶものなのに、無理やり第一章、二章と順番に進めようとすると相手は「聞いてくれていたのかな」と寂しい気持ちになる。
うまくいかない日もあるが、その場合は相手の文化やモードに自分が合わせることで対応すると語った。
強引に引っ張るより、ひたすら温めて相手のペースに合わせる「北風と太陽」のアプローチを基本としている。
● 話し方の語尾と間の取り方の重要性
秀島氏は語尾にその人の個性が出ると考えており、武田氏の「何ですかねー」という質問の振り方は相手を追い込まず余白を残すトーンだと分析した。
安住紳一郎氏の「さて」の間が絶妙すぎると例に挙げ、沈黙の後の場面転換が見事だと評価した。
ラジオでは「何秒空いたら放送事故」という都市伝説があるが、実際にはそんなことはないと語った。
言葉を探す間は、聞いている人にとっても情報を整理するための「踊り場」になり、箸休めの役割を果たすと説明した。
ずっと集中して聞かせるギチギチの放送は疲れてしまうため、抜き所や余白を作ることが大切だと強調した。
● 番組クロージングと自然な終わり方
インタビューの終わりに無理にうまく締めようとする必要はなく、「時間ですね」という自然な流れで終わればいいと秀島氏が語った。
お弁当のおかずに例えて、プチトマトを転がしておくような余白が全体を最後まで支えてくれると説明した。
武田氏が著書の内容を引用し、終わり方を考えすぎる必要はないという秀島氏の考え方を確認した。
「またお願いします」という挨拶で終わる自然な形が最も良いという結論に至った。