【インタビュー・サマリー】 ※誤字・脱字はご容赦を
● ゲスト紹介とTシャツ研究のきっかけ
本日のゲストは「Tシャツの日本史」の著者、高畑鍬名氏で、タックイン研究家という肩書きを持つ専門家である。
 高畑氏は文学部出身で、Tシャツ全般ではなくシャツの裾を入れるか出すかという「タックイン」に特化した研究を行っている。
研究のきっかけは大学時代に映画の衣装助手として現場に入り、台本にはあまり書かれていない衣装について深く考えるようになったことである。
大学に戻ってから小説や漫画の衣装を分析する中で、Tシャツの裾が作家の無意識を反映していることに気づいた。
高校時代は私服校に通い、高円寺で1900円程度の変なTシャツを購入して周囲を笑わせる「出落ちTシャツ」を楽しんでいた。
ダサいTシャツが持つパワーや、ダサいファッションが人を笑顔にする力を高校生の頃から体験していた。
● Tシャツの歴史と日本への導入
日本に洋服がやってきたのは1860年代頃で、福沢諭吉が西洋のライフスタイルを紹介するパンフレットを作成した。
そのパンフレットにはシャツを「ショルツ」、アンダーシャツを「オンドルショルツ」として紹介しており、肌着として最初期から存在していた。
夏目漱石や永井荷風も著作の中で、肌着は人前で見せるものではないと記述しており、当時は下着としての認識が強かった。
現代のようにTシャツ一枚で社交の場や公の場に出るようになったのは比較的最近のことである。
今和次郎氏の「ジャンパーを着て四十年」という本があり、冠婚葬祭でもジャンパーで行くという姿勢に共感を持っている。
高畑氏は文学部出身で、Tシャツ全般ではなくシャツの裾を入れるか出すかという「タックイン」に特化した研究を行っている。
研究のきっかけは大学時代に映画の衣装助手として現場に入り、台本にはあまり書かれていない衣装について深く考えるようになったことである。
大学に戻ってから小説や漫画の衣装を分析する中で、Tシャツの裾が作家の無意識を反映していることに気づいた。
高校時代は私服校に通い、高円寺で1900円程度の変なTシャツを購入して周囲を笑わせる「出落ちTシャツ」を楽しんでいた。
ダサいTシャツが持つパワーや、ダサいファッションが人を笑顔にする力を高校生の頃から体験していた。
● Tシャツの歴史と日本への導入
日本に洋服がやってきたのは1860年代頃で、福沢諭吉が西洋のライフスタイルを紹介するパンフレットを作成した。
そのパンフレットにはシャツを「ショルツ」、アンダーシャツを「オンドルショルツ」として紹介しており、肌着として最初期から存在していた。
夏目漱石や永井荷風も著作の中で、肌着は人前で見せるものではないと記述しており、当時は下着としての認識が強かった。
現代のようにTシャツ一枚で社交の場や公の場に出るようになったのは比較的最近のことである。
今和次郎氏の「ジャンパーを着て四十年」という本があり、冠婚葬祭でもジャンパーで行くという姿勢に共感を持っている。
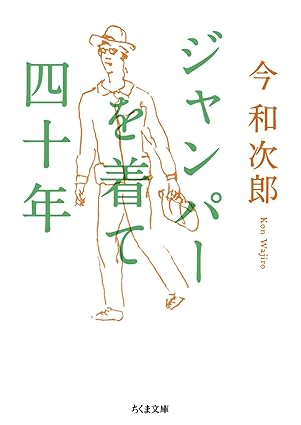 かしこまった格好で伝わる誠意ではなく、心の中の誠意を大切にするという考え方がある。
● Tシャツファッションの時代変遷
1970年代に日本の若者たちがデートでもシャツとジーンズで出かけるようになり、カジュアル化が進んだ。
1980年代に入ると大学生はアメリカ的なポロシャツやゴルフシャツを嫌い、一時的に着用が減少した。
1980年代後半から90年代にかけて「シブカジ」と呼ばれるジーンズとTシャツのスタイルが若者の間で流行し、裾を出し始めた。
DCファッションの時代には若者がジャケットを着ないと歩けない風潮があったが、その後は二度と戻らなかった。
尾崎豊や吉田栄作のシンプルなジーンズとTシャツスタイルは、前世代のきらびやかなチェッカーズ的ファッションへのカウンターとして機能した。
流行は常に前の世代の価値観をひっくり返す快感を伴っており、シンプル化と装飾化を繰り返している。
● タックインブームとその変遷
2010年代前半から2015年頃にかけてタックインがピークを迎え、とんがったファッションとして流行した。
2025年現在はタックインの熱が少し下がっており、原宿などではまだタックインの若者が多く見られる。
現在は「チビT期」と呼ばれる時期で、ショート丈のTシャツやへそ出しファッションがトレンドになっている。
特に女性はKPOPの影響でおへそを出して街を歩くのが当たり前になっており、徐々に男性にもその流れが来ている。
1982年生まれと1984年生まれの世代は、中学時代に制服のワイシャツの裾を出すことに命がけで取り組んでいた。
制服の着崩しは先生に対するコントロールが及ばない聖域を作る行為であり、ちゃんとしたくないという快感や大人をギョッとさせる快感があった。
● 電車男とタックインのイメージ
2005年に公開された「電車男」は、オタクのダサいファッションの象徴としてシャツをインするスタイルを描いた。
当時20歳だった世代が現在40歳となり、電車男的な世界観の残像によってタックインできない人が多い。
電車男から2025年で20周年を迎え、おめでたいアニバーサリーイヤーとなっている。
若い世代がタックインしていると、上の世代が「それダサいって言われてたやつだよ」と指摘してしまう。
逆に若い世代からは「今はTシャツ出してる方がダサい」と反撃されることもある。
この本を読むことで、読者の中に新しい同調圧力が生まれてしまい、道行く人の裾やアニメの裾が気になるようになる。
● アニメ・漫画作品における裾の研究
美味しんぼなどの長期連載作品では、必ず裾を出すタイミングが訪れることを詳細に調査した。
アニメ作品では主要キャラクターは作者が念入りに描くが、背景キャラクターはアシスタントが描くため時代考証がガチャつく。
U-NEXTの0.6倍速やコマ送り機能を使って、アニメの裾が出ているかどうかを確認する作業を行った。
メインの製作者が40歳でもアシスタントが25歳だと、背景キャラクターの裾の扱いが異なることがある。
高畑氏が以前アニメの仕事をしていた際、背景の人々が白いパンツを履きすぎていると指摘してドン引きされた経験がある。
読者がこの本を読んだ後、自発的にゴジラや北の国からなど様々な作品の裾を調査し始めている。
● サッカーユニフォームと裾の規定
1993年のJリーグ開幕当初、木村和司などのベテラン選手はユニフォームの裾を入れていたが、ラモス瑠偉などの不良性のある選手は出していた。
サッカー部では裾を出すのがかっこいいという認識があり、練習中は出すが試合時は入れるなどのグラデーションがあった。
2006年に日本サッカー協会がTシャツの裾は入れてプレーするようにというお達しを出した。
2012年には世界水準では裾を出しているため、出してもいいという逆のお達しが出された。
この2012年という時期は、菅田将暉氏がメディアでタックインを始めた時期と重なっている。
ダサいをかっこよくするという反転は実力者にしかできないことであり、菅田将暉氏がその火付け役となった。
● 無名の流行と襟の権威性
シブカジの前にも無名の若者たちがストリートスナップで裾を出しており、誰が始めたか名指しできない流行が存在した。
日本には名前のない流行が二つあり、それがTシャツの裾出しのタイミングと2010年代の入れるタイミングである。
無名の若者が始めた流行のため記録が残っておらず、透明な流行として存在している。
襟に関しては、ハイカラのハイは襟が高いという意味で、権威の象徴として今も続いている。
無地のTシャツとかりゆしウェアを比較すると、襟があるだけでかりゆしウェアの方が正式な場に適しているとされる。
日本の若者文化には「バンカラ」というアンチファッションの伝統が水脈のように流れ続けている。
● 今後の研究と映画化の構想
高畑氏は大学の所属ではなく普通の会社員をしながら研究を続けており、元々は自主映画を撮影していた。
今後は「劇場版Tシャツの日本史」として、Tシャツの裾を入れるか入れないか話し合う電車男のような短編映画を撮りたいと考えている。
映画の中には細かいところに歴史と違う偽物を入れて、観客が「ここで仕掛けてきたな」と気づく仕掛けを考えている。
大谷翔平の画像がいっぱい敷き詰められたTシャツなど、総柄のTシャツはよく行けるなと思うデザインの代表例である。
この本を出したことで、読者に新たな同調圧力を植え付けてしまったが、本来は同調圧力を解体するために書いた本だった。
すべてのTシャツは好きなように着るべきであり、バンドを聴いていなくてもバンドTシャツを着ていいという自由な姿勢を提唱している。
かしこまった格好で伝わる誠意ではなく、心の中の誠意を大切にするという考え方がある。
● Tシャツファッションの時代変遷
1970年代に日本の若者たちがデートでもシャツとジーンズで出かけるようになり、カジュアル化が進んだ。
1980年代に入ると大学生はアメリカ的なポロシャツやゴルフシャツを嫌い、一時的に着用が減少した。
1980年代後半から90年代にかけて「シブカジ」と呼ばれるジーンズとTシャツのスタイルが若者の間で流行し、裾を出し始めた。
DCファッションの時代には若者がジャケットを着ないと歩けない風潮があったが、その後は二度と戻らなかった。
尾崎豊や吉田栄作のシンプルなジーンズとTシャツスタイルは、前世代のきらびやかなチェッカーズ的ファッションへのカウンターとして機能した。
流行は常に前の世代の価値観をひっくり返す快感を伴っており、シンプル化と装飾化を繰り返している。
● タックインブームとその変遷
2010年代前半から2015年頃にかけてタックインがピークを迎え、とんがったファッションとして流行した。
2025年現在はタックインの熱が少し下がっており、原宿などではまだタックインの若者が多く見られる。
現在は「チビT期」と呼ばれる時期で、ショート丈のTシャツやへそ出しファッションがトレンドになっている。
特に女性はKPOPの影響でおへそを出して街を歩くのが当たり前になっており、徐々に男性にもその流れが来ている。
1982年生まれと1984年生まれの世代は、中学時代に制服のワイシャツの裾を出すことに命がけで取り組んでいた。
制服の着崩しは先生に対するコントロールが及ばない聖域を作る行為であり、ちゃんとしたくないという快感や大人をギョッとさせる快感があった。
● 電車男とタックインのイメージ
2005年に公開された「電車男」は、オタクのダサいファッションの象徴としてシャツをインするスタイルを描いた。
当時20歳だった世代が現在40歳となり、電車男的な世界観の残像によってタックインできない人が多い。
電車男から2025年で20周年を迎え、おめでたいアニバーサリーイヤーとなっている。
若い世代がタックインしていると、上の世代が「それダサいって言われてたやつだよ」と指摘してしまう。
逆に若い世代からは「今はTシャツ出してる方がダサい」と反撃されることもある。
この本を読むことで、読者の中に新しい同調圧力が生まれてしまい、道行く人の裾やアニメの裾が気になるようになる。
● アニメ・漫画作品における裾の研究
美味しんぼなどの長期連載作品では、必ず裾を出すタイミングが訪れることを詳細に調査した。
アニメ作品では主要キャラクターは作者が念入りに描くが、背景キャラクターはアシスタントが描くため時代考証がガチャつく。
U-NEXTの0.6倍速やコマ送り機能を使って、アニメの裾が出ているかどうかを確認する作業を行った。
メインの製作者が40歳でもアシスタントが25歳だと、背景キャラクターの裾の扱いが異なることがある。
高畑氏が以前アニメの仕事をしていた際、背景の人々が白いパンツを履きすぎていると指摘してドン引きされた経験がある。
読者がこの本を読んだ後、自発的にゴジラや北の国からなど様々な作品の裾を調査し始めている。
● サッカーユニフォームと裾の規定
1993年のJリーグ開幕当初、木村和司などのベテラン選手はユニフォームの裾を入れていたが、ラモス瑠偉などの不良性のある選手は出していた。
サッカー部では裾を出すのがかっこいいという認識があり、練習中は出すが試合時は入れるなどのグラデーションがあった。
2006年に日本サッカー協会がTシャツの裾は入れてプレーするようにというお達しを出した。
2012年には世界水準では裾を出しているため、出してもいいという逆のお達しが出された。
この2012年という時期は、菅田将暉氏がメディアでタックインを始めた時期と重なっている。
ダサいをかっこよくするという反転は実力者にしかできないことであり、菅田将暉氏がその火付け役となった。
● 無名の流行と襟の権威性
シブカジの前にも無名の若者たちがストリートスナップで裾を出しており、誰が始めたか名指しできない流行が存在した。
日本には名前のない流行が二つあり、それがTシャツの裾出しのタイミングと2010年代の入れるタイミングである。
無名の若者が始めた流行のため記録が残っておらず、透明な流行として存在している。
襟に関しては、ハイカラのハイは襟が高いという意味で、権威の象徴として今も続いている。
無地のTシャツとかりゆしウェアを比較すると、襟があるだけでかりゆしウェアの方が正式な場に適しているとされる。
日本の若者文化には「バンカラ」というアンチファッションの伝統が水脈のように流れ続けている。
● 今後の研究と映画化の構想
高畑氏は大学の所属ではなく普通の会社員をしながら研究を続けており、元々は自主映画を撮影していた。
今後は「劇場版Tシャツの日本史」として、Tシャツの裾を入れるか入れないか話し合う電車男のような短編映画を撮りたいと考えている。
映画の中には細かいところに歴史と違う偽物を入れて、観客が「ここで仕掛けてきたな」と気づく仕掛けを考えている。
大谷翔平の画像がいっぱい敷き詰められたTシャツなど、総柄のTシャツはよく行けるなと思うデザインの代表例である。
この本を出したことで、読者に新たな同調圧力を植え付けてしまったが、本来は同調圧力を解体するために書いた本だった。
すべてのTシャツは好きなように着るべきであり、バンドを聴いていなくてもバンドTシャツを着ていいという自由な姿勢を提唱している。



