【インタビュー・サマリー】 ※誤字・脱字はご容赦を
ジャーナリスト・ノンフィクション作家の清武英利氏が、新著『記者は天国に行けない 反骨のジャーナリズム戦記』を通じて語った、自身の経歴、ジャーナリズムの精神、現代メディアへの課題認識について詳細にまとめたものです。
 ● ゲスト紹介と清武氏のキャリア
経歴のハイライト: 1950年宮崎県生まれ。1975年に読売新聞社に入社し、社会部記者として警視庁、国税庁を担当し、長年スクープを報じた実績を持つ 。
転機: 2004年から読売巨人軍球団代表に就任するが、2011年に球団代表兼ゼネラルマネージャーを解任された 。
現在の活動: 現在はノンフィクション作家として活動し、『しんがり 山一証券最後の十二人』『石つぶて』『アトムの心臓』など多数の著作を発表している 。
「三つ目の人生」: 現在を新聞記者、野球経営者、ノンフィクション作家という「三つ目の人生」と捉えている。
● ゲスト紹介と清武氏のキャリア
経歴のハイライト: 1950年宮崎県生まれ。1975年に読売新聞社に入社し、社会部記者として警視庁、国税庁を担当し、長年スクープを報じた実績を持つ 。
転機: 2004年から読売巨人軍球団代表に就任するが、2011年に球団代表兼ゼネラルマネージャーを解任された 。
現在の活動: 現在はノンフィクション作家として活動し、『しんがり 山一証券最後の十二人』『石つぶて』『アトムの心臓』など多数の著作を発表している 。
「三つ目の人生」: 現在を新聞記者、野球経営者、ノンフィクション作家という「三つ目の人生」と捉えている。
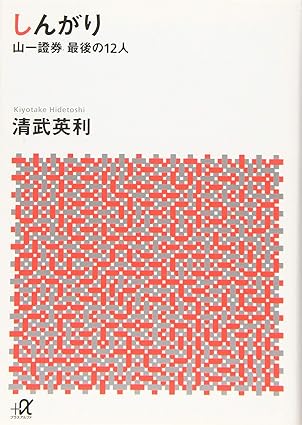
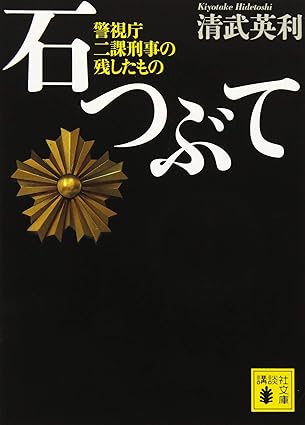
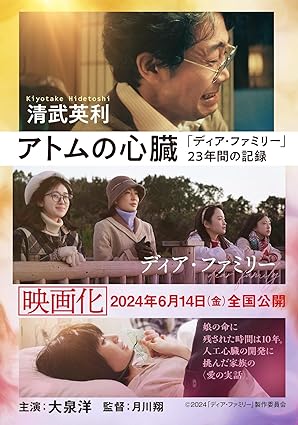 ● 執筆の動機と目的
社会状況への応答: 「マスゴミ」「オールドメディア」という批判が飛び交う時代に、メディア最前線で働く人々の顔や考えを書き残したいと考えた 。
編集者からの示唆: 当初は回顧録を書くつもりはなかったが、文藝春秋の編集長に「今でしょ」と挑発され、執筆を決意した 。
著書の内容構成: 編集者の強い勧めにより、奮闘する現役記者の姿を追うことだけでなく、自身のキャリア(渡辺恒雄氏との対立、再起)や先輩記者たちのことも含めて記述することになった 。
メディア観: メディアには「新しいも古いもなく、中身だけがある」という信念のもと、現場で頑張る記者たちの奮闘を書き残すことを目的とした。
● ジャーナリズムの「精神」と「姿勢」
「弱い方につく」という教え: 青森支局のデスクから「どちらの言い分が正しいか筆に迷ったら、弱い方につくんだ」という教えを受け、これを基本姿勢としている 。
権力の監視者: コラムニストからも「政府と庶民だったら庶民、男と女だったら女の味方につけ」という指導を受け、権力の監視者として、常に視線を低くして生きることの重要性を学んだ 。
反骨の表現: 「牙のある雑草の一本でありたい」という姿勢を持つ 。大先輩の本多勝一氏も「野グソのようでありたい」と表現し、権力への抵抗姿勢を示していた 。
記者文化の伝承: 地方支局には、入社時に既に退社していた本多氏の「酔いどれ記者」のような、熱い記者文化の雰囲気が残っていた 。
● 渡辺恒雄氏と読売新聞の独裁体制
違和感の表明: 渡辺恒雄氏が亡くなった際の「偉業を持ち上げる報道ばかり」に違和感を持った 。
IT音痴とメディアのトップ: SNS時代に、スマホもパソコンも使わないIT音痴の人物がメディアのトップでいることへの疑問があった 。
「独裁者」発言: 渡辺氏は自ら「俺は独裁者だ」「俺は最後の独裁者だ」と平気で発言し、社長を含む幹部を怒鳴りつけることが日常的だった 。
「社論」への反論: 一人の考えで紙面を一色に染めることに反対し、いろんな人がいろんな意見を言うことがメディアの面白さだと主張する 。
● 現代メディアの課題と「記録の義務」
スクープの風化: 森友・加計・桜を見る会・裏金問題など、新聞社のスクープが結果的にうやむやになってしまうケースが続いていると指摘 。
「本にする義務」: 特ダネを取った記者には、連載をし、本にまとめる資格と義務があると主張する 。
記憶の定着: 新聞は「日稼ぎ」(書いては飛ばしを繰り返す)で終わらせず、大事件から半年や一年経っても「あれなんだっけ?」とならないよう、本という形で残すことが重要である 。
記者への情熱要求: 出版社に対して「これを本に残してくれ」という努力と情熱が記者に必要だと考える 。
● 技の伝承と若手への期待
伝承の欠如: メディアの世界ほど技の伝承が少ない世界はないと指摘する。
指導の重要性: 青森支局長による毎週日曜日の厳しい原稿指導の経験から、「神はディテールに宿る」を実践で教える人の存在が重要であると語る 。
若手の可能性: 20代でも掘り下げる力は十分にあり、記者クラブにいる特ダネ記者だけでなく、様々な立場の記者が時代を象徴するスクープを書いていると信じている 。
「爪痕」を残すこと: 若手記者に対し、一生に一度の人生で「生きた爪痕」を残してほしいと訴える 。
発信手段の多様化: SNSやnote、THE LETTERなど多様な発信手段を活用しながら、取材内容を記録し続けることに期待を寄せている 。
● 執筆の動機と目的
社会状況への応答: 「マスゴミ」「オールドメディア」という批判が飛び交う時代に、メディア最前線で働く人々の顔や考えを書き残したいと考えた 。
編集者からの示唆: 当初は回顧録を書くつもりはなかったが、文藝春秋の編集長に「今でしょ」と挑発され、執筆を決意した 。
著書の内容構成: 編集者の強い勧めにより、奮闘する現役記者の姿を追うことだけでなく、自身のキャリア(渡辺恒雄氏との対立、再起)や先輩記者たちのことも含めて記述することになった 。
メディア観: メディアには「新しいも古いもなく、中身だけがある」という信念のもと、現場で頑張る記者たちの奮闘を書き残すことを目的とした。
● ジャーナリズムの「精神」と「姿勢」
「弱い方につく」という教え: 青森支局のデスクから「どちらの言い分が正しいか筆に迷ったら、弱い方につくんだ」という教えを受け、これを基本姿勢としている 。
権力の監視者: コラムニストからも「政府と庶民だったら庶民、男と女だったら女の味方につけ」という指導を受け、権力の監視者として、常に視線を低くして生きることの重要性を学んだ 。
反骨の表現: 「牙のある雑草の一本でありたい」という姿勢を持つ 。大先輩の本多勝一氏も「野グソのようでありたい」と表現し、権力への抵抗姿勢を示していた 。
記者文化の伝承: 地方支局には、入社時に既に退社していた本多氏の「酔いどれ記者」のような、熱い記者文化の雰囲気が残っていた 。
● 渡辺恒雄氏と読売新聞の独裁体制
違和感の表明: 渡辺恒雄氏が亡くなった際の「偉業を持ち上げる報道ばかり」に違和感を持った 。
IT音痴とメディアのトップ: SNS時代に、スマホもパソコンも使わないIT音痴の人物がメディアのトップでいることへの疑問があった 。
「独裁者」発言: 渡辺氏は自ら「俺は独裁者だ」「俺は最後の独裁者だ」と平気で発言し、社長を含む幹部を怒鳴りつけることが日常的だった 。
「社論」への反論: 一人の考えで紙面を一色に染めることに反対し、いろんな人がいろんな意見を言うことがメディアの面白さだと主張する 。
● 現代メディアの課題と「記録の義務」
スクープの風化: 森友・加計・桜を見る会・裏金問題など、新聞社のスクープが結果的にうやむやになってしまうケースが続いていると指摘 。
「本にする義務」: 特ダネを取った記者には、連載をし、本にまとめる資格と義務があると主張する 。
記憶の定着: 新聞は「日稼ぎ」(書いては飛ばしを繰り返す)で終わらせず、大事件から半年や一年経っても「あれなんだっけ?」とならないよう、本という形で残すことが重要である 。
記者への情熱要求: 出版社に対して「これを本に残してくれ」という努力と情熱が記者に必要だと考える 。
● 技の伝承と若手への期待
伝承の欠如: メディアの世界ほど技の伝承が少ない世界はないと指摘する。
指導の重要性: 青森支局長による毎週日曜日の厳しい原稿指導の経験から、「神はディテールに宿る」を実践で教える人の存在が重要であると語る 。
若手の可能性: 20代でも掘り下げる力は十分にあり、記者クラブにいる特ダネ記者だけでなく、様々な立場の記者が時代を象徴するスクープを書いていると信じている 。
「爪痕」を残すこと: 若手記者に対し、一生に一度の人生で「生きた爪痕」を残してほしいと訴える 。
発信手段の多様化: SNSやnote、THE LETTERなど多様な発信手段を活用しながら、取材内容を記録し続けることに期待を寄せている 。