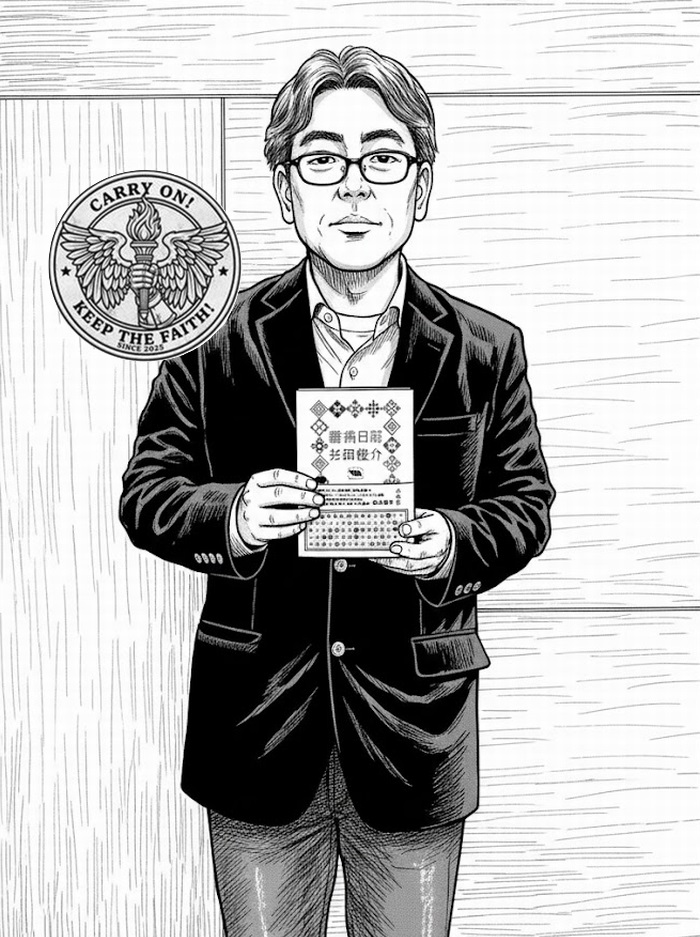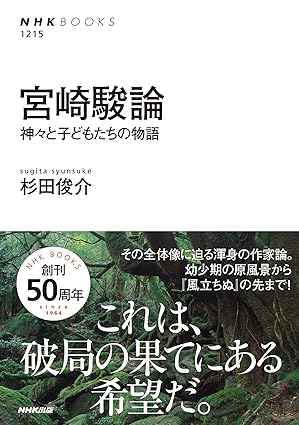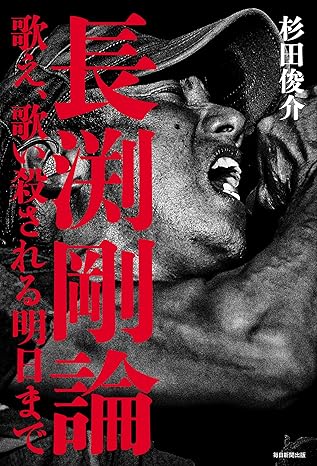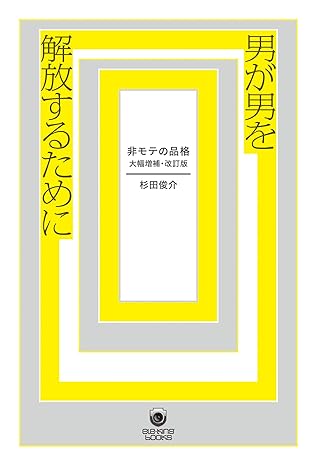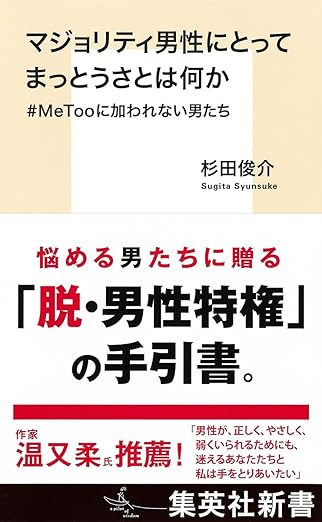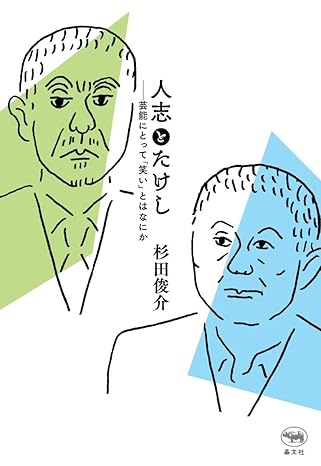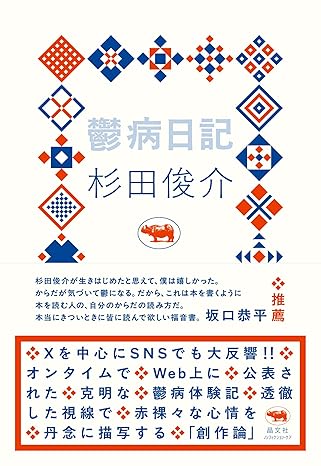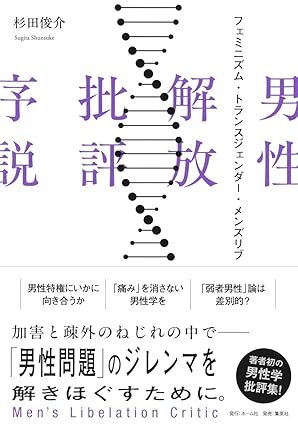【インタビュー・サマリー】 ※誤字・脱字はご容赦を
■ 杉田俊介の経歴と活動
批評家・杉田俊介氏は1975年生まれ。
2005年『フリーターにとって自由とは何か?』でデビューして以降、文学・アニメ・マンガ・社会問題・ジェンダー・労働などを対象に、幅広い批評活動を展開してきた。
過去の主な著書に『宮崎駿論』『長渕剛論』『非モテの品格』『マジョリティ男性にとって「まっとうさ」とは何か?』『ひとしとたけし 芸能にとって笑いとは何か』(晶文社)などがある。
2024年には、自身の鬱病記『鬱病日記』と、男性学批評集『男性解放批評序説』(いずれも晶文社)を刊行した。
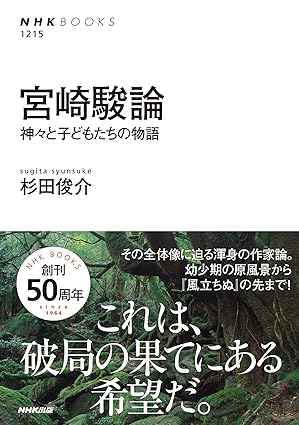
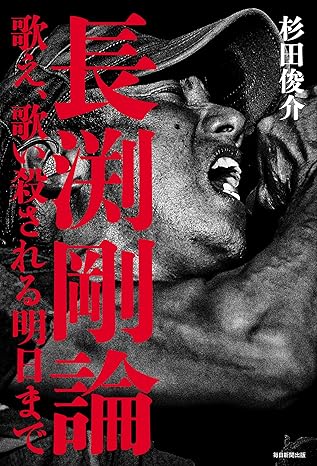
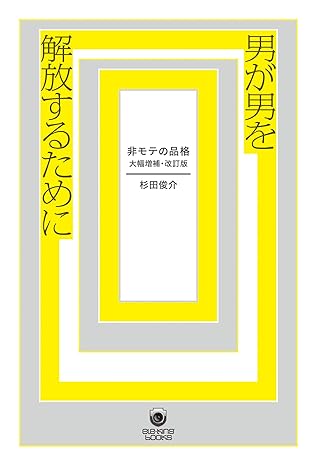
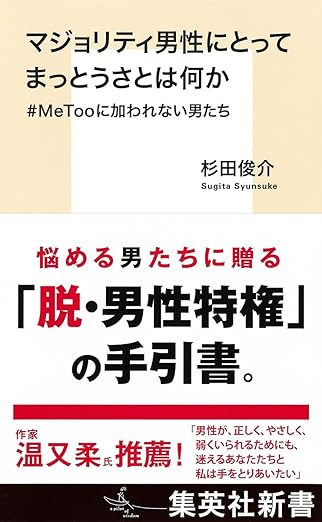
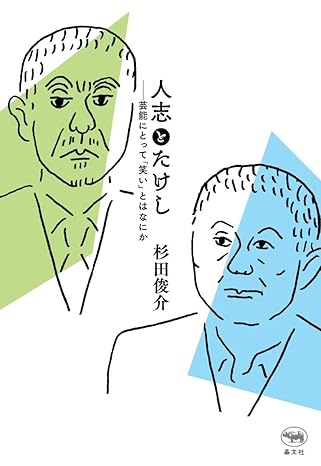
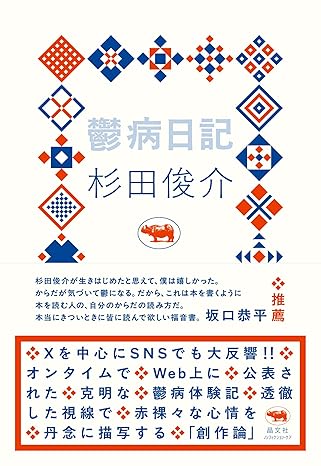
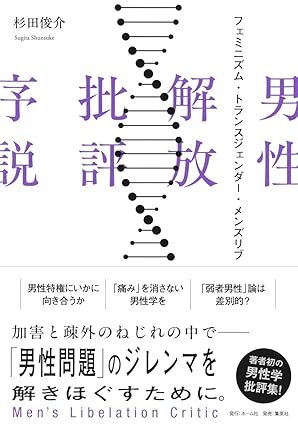 ■ 鬱病発症と「体の信号」
杉田氏は2023年暮れ頃、急に心身の異変を感じた。
電車に乗ると突然心臓が激しく鼓動し、息が荒くなる。目的地までたどり着けず途中下車を繰り返すようになったという。
当初は原因がわからず、「精神的な疲れだろう」と思っていたが、次第に体調全体が悪化。
12月中旬に心療内科を受診し、鬱病と診断された。
もともと「悲観的に物事を考える傾向がある」と自己分析し、社会を批判的に観察する思考様式が、長年にわたり自身を追い詰めていったのではないかと振り返る。
「批評家という仕事は、常に疑い、問いを立てる性質をもつ。肯定よりも懐疑から入る姿勢が、メンタルに悪影響を及ぼす面もある」と語った。
■ 「働きすぎ」と自己追い込み
発症直前まで、杉田氏は複数の媒体で執筆を続け、明らかに多忙だった。
「仕事を断ったら忘れられるのでは」「干されるのでは」という恐怖心が常にあり、フリーランスゆえの不安が、断れない心理につながっていたという。
「仕事をやめることが存在の喪失につながる」感覚は、同じく物書きの武田氏も共感を示した。
さらに、自身の内面には「能力主義」的な価値観が根深く残っていたと語る。
「他者との競争意識」や「自己実現しなければならない」という焦りが、言葉の上では否定していても、深層心理にはこびりついていたという。
その矛盾が鬱病発症後に強く意識され、「能力を基準とする社会の呪縛」を痛感した。
■ 「内なる優生思想」への気づき
杉田氏は、かつて障害者支援NPOで働いていた経験から、1970年代の障害者運動における「自己差別(障害者が障害者を差別する)」という問題を参照する。
人は外部からの差別だけでなく、自らの内面にある差別意識によっても苦しむ。
鬱病においても、「働けない自分」や「能力のない自分」を否定してしまう無意識が存在し、それこそが病の根源的な苦しみであると指摘する。
「鬱病を社会的に理解すること」と「自分の内なる価値観を解きほぐすこと」の両立が必要だと語った。
■ 鬱病の実感:「脳の病気」としての現実
杉田氏は「鬱病は心の弱さではなく、脳の病だと実感した」と述べる。
発症中は強い虚無感に支配され、「自分の人生はもう終わっている」と感じた。
これまで積み重ねた仕事、家族との関係などすべてが無意味に思え、「お前は生きていても意味がない」という声が頭の中で響く感覚が続いたという。
外出中に「車に飛び込みたい衝動」に駆られることもあり、自らの危険性を自覚して病院を受診。
「理性や意思ではどうにもできない」「自分をコントロールできない」感覚が、脳機能の問題としての鬱病を強く認識させたという。
■ 比較・一般化の危険性
「自分の鬱病が軽いのか重いのか分からない」と日記に記した杉田氏は、他人との比較がいかに有害かを強調した。
「他人はもっと重症なのに自分はまだ軽いから頑張れるはずだ」と思うことが、逆に自分を追い詰めてしまう。
「比較すること自体が、鬱病のスパイラルを深める要因になる」と語った。
■ SNS発信の意味
杉田氏は、鬱病中もSNSで自身の状態を発信していた。
一般的には「鬱病とSNSは相性が悪い」と言われるが、彼の場合はむしろ「言語化によって客観視できた」「支援的な反応が多かった」と語る。
同じ苦しみを持つ人々との交流が助けになり、攻撃的な反応は想像より少なかったという。
ただし、「他人に推奨できる方法ではない」と慎重に述べた。
■ 入院生活と「小さな生きがい」
精神科の開放病棟に入院した際、病院食は味気なく、やることもほとんどなかった。
そのなかで「こっそりおやつにトッポを食べる」など、些細な楽しみを見つけながら日々を過ごした。
敷地内のウォーキングなど、微細な生活の工夫が回復の支えになったという。
退屈と「何もしたくない時間」に向き合うことは大変だったが、「鬱病リアリズム(抑鬱リアリズム)」という概念を通じ、悲観的であることにも意味を見出した。
「現実を過度にポジティブに解釈せず、ありのまま受け止めることが、むしろ現実的な生き方を支えることもある」と語る。
■ 「回復ストーリー」への違和感
鬱病を扱った作品や漫画の多くが「回復して元気になった」物語であることに対し、杉田氏は違和感を表明。
「鬱病の日常は、回復のストーリーに乗らない。寛解(症状の和らぎ)はあっても、完全な回復はない病気。だからこそ“付き合い続ける生き方”が必要だ」と述べる。
「鬱病と共に生きる」姿勢は、「社会復帰」や「成果」を前提とした回復観とは異なる。
フリーライターという職業上、「何をもって回復とするのか」が定義しにくく、その曖昧さも苦しみの一因になったという。
■ 能力主義・男性性への批判
鬱病の経験を通じて、杉田氏は改めて「能力主義」「健常者中心主義」を問い直した。
成果や効率が絶対視される社会の中で、男性ほど「能力で評価されねばならない」という圧力を受けやすい。
「障害者差別はいけないと言いつつ、能力を肯定してしまう」という矛盾が、最も根深い社会的問題だと指摘する。
『男性解放批評序説』では、「体を壊してこそ一人前」という男らしさの神話を批判し、「自分の体や感情に鈍感であること」が男性をも苦しめていると述べる。
それは他者にも同様の無神経さを押しつける構造であり、「男性問題と鬱病は密接に絡み合っている」と分析する。
■ 「弱者男性論」への視点
近年の「弱者男性論」にも触れ、「女性やリベラルを攻撃する形で自己正当化する論調」に警鐘を鳴らす。
「男性も傷ついている」という主張が、被害者意識の拡大に陥る危険を指摘し、「女性が悪い」「社会が悪い」といった単純な敵対構造ではなく、個々の男性が自分の痛みや脆さを正直に見つめ、
他者と共有していくプロセスが必要だと語る。
そのために、「男はつらい」ではなく「私にとって男であることがつらい」と語る表現の違いを重視。
主語を小さくし、経験を個人の言葉として発することの重要性を強調した。
■ 「鬱病」からの洞察と希望
杉田氏は、鬱病を通して「自分の中の加害性や被害性、能動と受動の複雑な絡み」を見つめたという。
それらを丁寧に言語化することが、鬱病を社会的排外主義(敵を作る思考)へ転化させないための防波堤になると考える。
「苦しみを単純な物語にせず、自分の中の矛盾を見つめ続ける」ことが、病との共存にも、社会批評にも通じるという。
また、表現行為——文章、俳句、音楽、絵など——を通じて、自分の苦しみを他者と共有することが、回復とは異なる意味での「救い」になりうると語った。
■ 結語
杉田俊介氏の語りは、鬱病を「個人の病」としてではなく、「社会の構造」「能力と価値の体系」「男性性の文化」と結びつけて捉え直す試みである。
彼の経験は、精神疾患・ジェンダー・労働・表現といった複数の領域を横断し「生きづらさ」の根にある社会的圧力を可視化する。
武田砂鉄氏との対話は、批評家としての知的誠実さと、個人としての脆さが交差する貴重な記録となっている。
■ 鬱病発症と「体の信号」
杉田氏は2023年暮れ頃、急に心身の異変を感じた。
電車に乗ると突然心臓が激しく鼓動し、息が荒くなる。目的地までたどり着けず途中下車を繰り返すようになったという。
当初は原因がわからず、「精神的な疲れだろう」と思っていたが、次第に体調全体が悪化。
12月中旬に心療内科を受診し、鬱病と診断された。
もともと「悲観的に物事を考える傾向がある」と自己分析し、社会を批判的に観察する思考様式が、長年にわたり自身を追い詰めていったのではないかと振り返る。
「批評家という仕事は、常に疑い、問いを立てる性質をもつ。肯定よりも懐疑から入る姿勢が、メンタルに悪影響を及ぼす面もある」と語った。
■ 「働きすぎ」と自己追い込み
発症直前まで、杉田氏は複数の媒体で執筆を続け、明らかに多忙だった。
「仕事を断ったら忘れられるのでは」「干されるのでは」という恐怖心が常にあり、フリーランスゆえの不安が、断れない心理につながっていたという。
「仕事をやめることが存在の喪失につながる」感覚は、同じく物書きの武田氏も共感を示した。
さらに、自身の内面には「能力主義」的な価値観が根深く残っていたと語る。
「他者との競争意識」や「自己実現しなければならない」という焦りが、言葉の上では否定していても、深層心理にはこびりついていたという。
その矛盾が鬱病発症後に強く意識され、「能力を基準とする社会の呪縛」を痛感した。
■ 「内なる優生思想」への気づき
杉田氏は、かつて障害者支援NPOで働いていた経験から、1970年代の障害者運動における「自己差別(障害者が障害者を差別する)」という問題を参照する。
人は外部からの差別だけでなく、自らの内面にある差別意識によっても苦しむ。
鬱病においても、「働けない自分」や「能力のない自分」を否定してしまう無意識が存在し、それこそが病の根源的な苦しみであると指摘する。
「鬱病を社会的に理解すること」と「自分の内なる価値観を解きほぐすこと」の両立が必要だと語った。
■ 鬱病の実感:「脳の病気」としての現実
杉田氏は「鬱病は心の弱さではなく、脳の病だと実感した」と述べる。
発症中は強い虚無感に支配され、「自分の人生はもう終わっている」と感じた。
これまで積み重ねた仕事、家族との関係などすべてが無意味に思え、「お前は生きていても意味がない」という声が頭の中で響く感覚が続いたという。
外出中に「車に飛び込みたい衝動」に駆られることもあり、自らの危険性を自覚して病院を受診。
「理性や意思ではどうにもできない」「自分をコントロールできない」感覚が、脳機能の問題としての鬱病を強く認識させたという。
■ 比較・一般化の危険性
「自分の鬱病が軽いのか重いのか分からない」と日記に記した杉田氏は、他人との比較がいかに有害かを強調した。
「他人はもっと重症なのに自分はまだ軽いから頑張れるはずだ」と思うことが、逆に自分を追い詰めてしまう。
「比較すること自体が、鬱病のスパイラルを深める要因になる」と語った。
■ SNS発信の意味
杉田氏は、鬱病中もSNSで自身の状態を発信していた。
一般的には「鬱病とSNSは相性が悪い」と言われるが、彼の場合はむしろ「言語化によって客観視できた」「支援的な反応が多かった」と語る。
同じ苦しみを持つ人々との交流が助けになり、攻撃的な反応は想像より少なかったという。
ただし、「他人に推奨できる方法ではない」と慎重に述べた。
■ 入院生活と「小さな生きがい」
精神科の開放病棟に入院した際、病院食は味気なく、やることもほとんどなかった。
そのなかで「こっそりおやつにトッポを食べる」など、些細な楽しみを見つけながら日々を過ごした。
敷地内のウォーキングなど、微細な生活の工夫が回復の支えになったという。
退屈と「何もしたくない時間」に向き合うことは大変だったが、「鬱病リアリズム(抑鬱リアリズム)」という概念を通じ、悲観的であることにも意味を見出した。
「現実を過度にポジティブに解釈せず、ありのまま受け止めることが、むしろ現実的な生き方を支えることもある」と語る。
■ 「回復ストーリー」への違和感
鬱病を扱った作品や漫画の多くが「回復して元気になった」物語であることに対し、杉田氏は違和感を表明。
「鬱病の日常は、回復のストーリーに乗らない。寛解(症状の和らぎ)はあっても、完全な回復はない病気。だからこそ“付き合い続ける生き方”が必要だ」と述べる。
「鬱病と共に生きる」姿勢は、「社会復帰」や「成果」を前提とした回復観とは異なる。
フリーライターという職業上、「何をもって回復とするのか」が定義しにくく、その曖昧さも苦しみの一因になったという。
■ 能力主義・男性性への批判
鬱病の経験を通じて、杉田氏は改めて「能力主義」「健常者中心主義」を問い直した。
成果や効率が絶対視される社会の中で、男性ほど「能力で評価されねばならない」という圧力を受けやすい。
「障害者差別はいけないと言いつつ、能力を肯定してしまう」という矛盾が、最も根深い社会的問題だと指摘する。
『男性解放批評序説』では、「体を壊してこそ一人前」という男らしさの神話を批判し、「自分の体や感情に鈍感であること」が男性をも苦しめていると述べる。
それは他者にも同様の無神経さを押しつける構造であり、「男性問題と鬱病は密接に絡み合っている」と分析する。
■ 「弱者男性論」への視点
近年の「弱者男性論」にも触れ、「女性やリベラルを攻撃する形で自己正当化する論調」に警鐘を鳴らす。
「男性も傷ついている」という主張が、被害者意識の拡大に陥る危険を指摘し、「女性が悪い」「社会が悪い」といった単純な敵対構造ではなく、個々の男性が自分の痛みや脆さを正直に見つめ、
他者と共有していくプロセスが必要だと語る。
そのために、「男はつらい」ではなく「私にとって男であることがつらい」と語る表現の違いを重視。
主語を小さくし、経験を個人の言葉として発することの重要性を強調した。
■ 「鬱病」からの洞察と希望
杉田氏は、鬱病を通して「自分の中の加害性や被害性、能動と受動の複雑な絡み」を見つめたという。
それらを丁寧に言語化することが、鬱病を社会的排外主義(敵を作る思考)へ転化させないための防波堤になると考える。
「苦しみを単純な物語にせず、自分の中の矛盾を見つめ続ける」ことが、病との共存にも、社会批評にも通じるという。
また、表現行為——文章、俳句、音楽、絵など——を通じて、自分の苦しみを他者と共有することが、回復とは異なる意味での「救い」になりうると語った。
■ 結語
杉田俊介氏の語りは、鬱病を「個人の病」としてではなく、「社会の構造」「能力と価値の体系」「男性性の文化」と結びつけて捉え直す試みである。
彼の経験は、精神疾患・ジェンダー・労働・表現といった複数の領域を横断し「生きづらさ」の根にある社会的圧力を可視化する。
武田砂鉄氏との対話は、批評家としての知的誠実さと、個人としての脆さが交差する貴重な記録となっている。